日本における1990年代後半以降の新自由主義政策とその帰結―税制を中心に
本記事では、1990年代後半以降の新自由主義政策に伴う所得税や法人税の減税、規制緩和がどのような階層に恩恵を与えたのか、国民生活にはどのような影響を与えたのかを考察したいと思います。
1 所得税の税率構造とその推移
まずは図1を見てください。この図を見ると、現在の所得税の税率構造は6段階となっています。最高税率に関して言えば40%です。2007年(平成19年、以下西暦)以前を見てみると、(イメージ図にはない部分も一部あります。財務省HP参照)1974年は19段階で最高税率は75%、59年は15段階で最高税率は70%、87年は12段階で最高税率は60%、88年は6段階で最高税率は60%となっています。89年は5段階で最高税率は50%、99年からは4段階で最高税率は37%となっています。こうしてみれば、所得税は全体的に見て減税傾向だということがわかります。ここで注目すべきなのは99年の減税で、これまでにない最も累進性の弱い税率構造となったことです。この減税は1999年、小渕内閣の時の第145国会で断行されたいわゆる「構造改革」の一つで、後述する法人税減税や労働法制の規制緩和もこれに含まれます。
図1
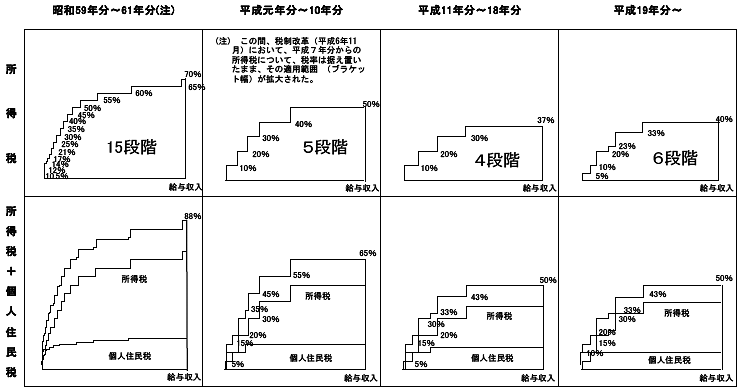
(出所:財務省HP)
では、租税負担率の推移はどうなっているのでしょうか。表1を見てください。まず、全体の租税負担率を見ると、日本は1965年の14.3%からピーク時の1990年には21.4%まで増加させました。しかし、2000年には17.2%に低下しています。参考までにOECD平均を見ると、1965年の21.1%から2000年の27.9%と上昇傾向であることから、日本の1990年代における租税負担率全体の低下が目立ちます。
次に個人所得税に関して見ると、日本は1965年の4.0%から上昇して1980年には6.1%、1990年には8.1%まで達しました。しかし、2000年には5.6%に低下しています。所得税の減税に伴って負担率も低下していることがわかります。
表1 日本とOECD平均の租税負担率の推移(GDP比、%)
|
日本 |
1965年 |
1980年 |
1990年 |
2000年 |
|
租税負担 |
14.3 |
17.8 |
21.4 |
17.2 |
|
個人所得税 |
4.0 |
6.1 |
8.1 |
5.6 |
|
法人所得税 |
4.1 |
5.5 |
6.5 |
3.6 |
|
OECD平均 |
1965年 |
1980年 |
1990年 |
2000年 |
|
租税負担 |
21.1 |
24.7 |
26.8 |
27.9 |
|
個人所得税 |
7.0 |
10.5 |
10.7 |
10.0 |
|
法人所得税 |
2.2 |
2.4 |
2.7 |
3.6 |
(出所:関野前掲書、49項より一部抜粋)
2 法人税の税率構造とその推移
次は図2を見てください。法人税も、全体的に見ると所得税と同様に減税傾向だということがわかります。また、平成10年には基本税率が34.5%、11年には30%と平成10年から11年にかけて大幅に減税されていることもわかります。
次に今一度、表1を見てください。法人所得税における租税負担率の推移を見てみると、1965年の4.1%から1990年の6.5%と上昇傾向です。しかし、2000年になると3.6%と急激に低下しています。これも所得税と同様に、減税の結果と言えるでしょう。
一方のOECD平均を見ると、1965年から1990年まで一貫して2%台で推移している。この点から、日本の法人所得税の負担はOECD平均の2倍以上と言うことができます。しかし、ここで注意したいのは、本来の法人負担を見るためには、法人所得税だけでなく、社会保障事業主負担も検討する必要があることです。表2によると、法人負担全体で1990年から2000年にかけて各国の社会保障事業主負担は上昇傾向にもかかわらず、日本は11.0%から8.6%へと低下しています。また、日本の全体の法人負担は、1990年まではOECD平均よりも高かったです。しかし、2000年にはOECD平均を下回っています。この点から、日本の法人負担は先進国の中でそれほど高いとは言えないことがわかります。
表2 法人所得税と社会保障事業主負担の推移(GDP比、%)
|
|
法人所得税 |
社会保障事業主負担 |
合計 |
|||||||||||
|
|
65 |
80 |
90 |
00 |
65 |
80 |
90 |
00 |
65 |
80 |
90 |
00 |
|
|
|
日本 |
4.1 |
5.5 |
6.5 |
3.6 |
1.7 |
3.7 |
4.5 |
5.0 |
5.8 |
9.2 |
11.0 |
8.6 |
|
|
|
アメリカ |
4.0 |
2.9 |
2.1 |
2.5 |
1.9 |
3.2 |
3.6 |
3.5 |
5.9 |
6.1 |
5.7 |
7.5 |
|
|
|
フランス |
1.8 |
2.1 |
2.3 |
3.2 |
8.7 |
11.5 |
11.7 |
11.3 |
9.9 |
13.6 |
14.0 |
16.0 |
|
|
|
スウェーデン |
2.1 |
1.2 |
1.7 |
4.1 |
3.1 |
13.1 |
14.0 |
11.9 |
5.2 |
14.3 |
15.7 |
16.0 |
|
|
|
OECD平均 |
2.2 |
2.4 |
2.7 |
3.6 |
2.7 |
4.6 |
4.8 |
5.7 |
4.9 |
7.0 |
7.5 |
9.3 |
|
|
(出所:関野前掲書、56頁より一部抜粋)
図2 法人税率の推移
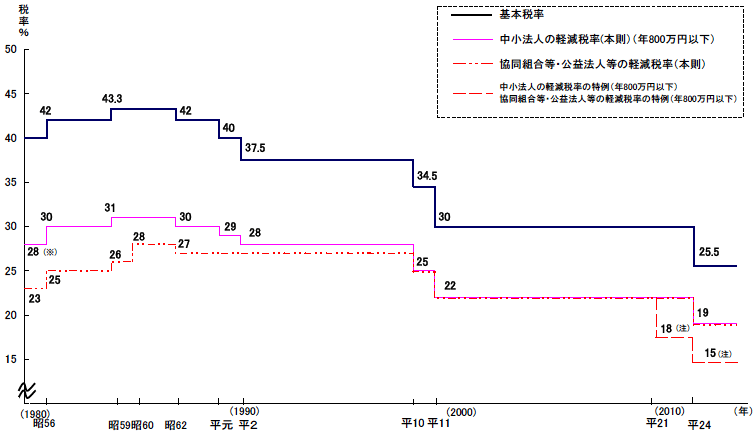
(出所:財務省HP)
3 労働法制の規制緩和
次に1990年代の労働法制の規制緩和について見てみましょう。この項で税制とは関係ないように見える労働法制の規制緩和を入れた理由としては2つあります。第1に新自由主義的な構造改革を検討する上で、税制改革だけでは語りきれないという点、第2に労働法制の規制緩和によって正規雇用が減少することで国民全体としての平均賃金が下落し、結果的に国民が支払う所得税収や消費税収が減少することが考えられるからです。
1995年、日本経営者団体連盟が「新時代の『日本的経営』」を発表しました。この文書は、雇用形態を長期蓄積能力活用型グループ、高度専門能力活用型グループ、雇用柔軟型グループの3つに分け、グループ別にその処遇の内容が変わるというものでした。これを皮切りに、労働者派遣法は次々に改正され、規制緩和が進行しました。労働者派遣法は、もともと事業の行える適用対象業務を限定する、いわゆるポジティブリスト方式として出発したもので、主として専門職が中心でした。しかし、1996年には業務が拡大され、事務職なども含まれるようになりました。ポイントとしては1999年の改正で、ポジティブリスト方式とは異なり、適用対象業務の限定を原則として撤廃し、原則自由化するネガティブリスト方式を採るものとなりました。更に2004年には、製造業も解禁されました。
4 帰結
では、第1節から第3節の帰結として、それぞれの政策が国民生活にどのような影響を与えたのでしょうか。
まずは所得税から見ていきましょう。所得税に関しては、第1節で指摘したように、累進税率が大幅に緩和され、税率のフラット化へとシフトしていきました。住民税率を含めても同じ流れです。こうした税率のフラット化は、勤労者階層などの負担軽減を名目として行われたのですが、実際にはどの所得階層が負担軽減の恩恵を受けたのでしょうか。表3を見てください。
表3 所得階級別の所得税・住民税の負担額・率
|
所得階級 |
1984年度 |
2000年度 |
84→00年度 |
|
500万円 |
39.5万円 7.9% |
11.5万円 2.3% |
-28.0万円 -5.6% |
|
700万円 |
89.1万円 12.7% |
31.9万円 4.6% |
-57.2万円 -8.1% |
|
2000万円 |
701.0万円 35.1% |
440.1万円 22.0% |
-260.9万円 -13.1% |
|
5000万円 |
2785.4万円 55.7% |
1839.8万円 36.8% |
-946.0万円 -18.9% |
注)給与所得者,夫婦子供2人(専業主婦)世帯。
(出所:関野前掲書、55頁、表2-5)
この表を見ると、84年度から2000年度にかけて、どの所得階層も減税の恩恵を受けていることがわかります。所得階層別に見ていくと、年収500万円の家庭では、金額ベースで見れば-28万円、割合で見れば-5.6%となっています。一方の年収5000万円の家庭では、金額ベースで見れば-946万円、割合で見れば-18.9%となっています。このことから、高所得者層ほど減税という負担軽減の恩恵を大きく受けていることがわかります。すなわち、所得再分配機能が著しく低下していると言ってよいでしょう。
次に法人税について見ていきます。法人税に関しては、第2節で指摘したように、先進国と比較してみると日本の法人負担が一概に大きいとは言えません。にもかかわらず、税負担の部分ばかりを強調して日本の法人負担は大きいと主張する財界やマスコミには疑問を抱かざるを得ません。こうした主張がまかり通って法人税を減税し、その減収分を消費税で賄うという手段は、結局のところ逆進性などのために低所得者ほど大きな負担を強いられることになるでしょう。
最後は労働法制の規制緩和です。前述した減税に加え、労働法制の規制緩和は、企業の国際競争力を高めることにつながりました。村上によれば、「国際的価格競争に直面して直接雇用の縮小した電機産業では非正規雇用の拡大によって実質生産額の増大が実現し、…競争力強化が可能になったものと捉えられる(注;村上、下記参考論文、77頁)」と指摘しています。更に、こうした輸出産業での雇用動向を踏まえ、「2000年代前半、輸出依存的成長産業での非正規雇用の拡大が比較的高賃金の直接雇用の抑制を招き、…直接雇用が大きく削減された(注;村上、下記参考文献、77頁)」と指摘しています。その結果、個人所得は減少を続け、それと連動して消費も停滞したことを明らかにしています。
まとめると、第1、2節の減税や第3節の労働法制の規制緩和といった、いわゆる「構造改革」の中での企業を主役とした新自由主義的なサプライサイド政策では、国民生活を改善することはできないということです。村上が指摘するように、日経連の「新時代の『日本的経営』」に象徴される雇用の弾力化によって輸出は伸長します。しかしながら、国際競争力を強化するために非正規雇用を増やすことは、所得の減少を促し、消費を弱めることにつながるので、国民目線で見ればむしろマイナスとなるのです。つまり、現代においていくら企業が競争力を強化して収益を伸ばしても、それが賃金に反映されにくい構造になっているのです。こうした現状があるにもかかわらず、未だに企業に頑張って収益を上げてもらおうとしている安倍政権の政策には、疑問を持たざるを得ません。
参考文献、資料
・後藤道夫『反「構造改革」』青木書店、2002年、106頁
・雇用のあり方研究会編『ディーセント・ワークと新福祉国家構想―人間らしい労働と生活を実現するために』旬報社、2011年、53-54頁
・関野満夫『日本型財政の転換 新自由主義的改革を超えて』青木書店、2003年、48-58頁
・高梨昌『第三版 詳解労働者派遣法』エイデル研究所、2007年、6-7頁。
・村上研一「日本の外需依存的再生産構造の特質と変容―産業連関表から推計した部門構成の考察を中心にして―」『季刊 経済理論』第48巻第2号、2011年7月、76-78頁
・財務省HP『法人税率の推移』http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/082.htm (閲覧日:2013年1月10日)
・同上『所得税の税率の推移(イメージ図)』http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/033.htm
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/035.htm
(閲覧日:2013年1月10日)




