戦後から現在までの概観と時期区分―高度成長期(1955-1975)
2-1均衡財政期
50年代中頃に入ると、本格的な経済成長の局面を迎えることとなりました。この経済成長は他の先進諸国に類をみないほどの成長率だったため、一般に「高度成長」と呼ばれています。高度成長がもたらされた要因としては、第1に日本経済の供給・需要の両サイドに源泉がありました。供給サイドでは、終戦後の海外からの帰国者とベビーブームを背景に、豊富な人口と高い教育水準が合わさって質の高い労働力が供給されました。また、家計の旺盛な貯蓄を背景に、設備投資が活発化することで生産能力を拡大しました。第2に、需要サイドの拡大も経済成長に重要な役割を果たしました。経済成長とともに賃金も順調に上昇したため、需要が急速に拡大した生産能力を十分に吸収し、高度成長の原動力となっていたのです。
第3に、政府主導の成長政策も重要です。50年代中頃以降、政府は経済成長を最大の目的とし、それを推進する立場を明確にしました。具体的には、「経済自立5ヵ年計画」を作成し、重要な政策目標として「成長、投資、輸出」の3つを結び付け、それを支援することを打ち出しました。これを達成するための手段として、石は①租税および政府支出政策②金融政策③財政投融資の活用④総需要拡大政策の堅持⑤経済安定より成長を志向の5つにまとめています(下記参考文献、172頁)。これは、後藤の言うところの「開発主義」(下記参考文献、130頁)と呼ぶことができます。
50年代中頃から60年代における高度成長と税・財政の関係については、詳細は改めて書くことにしますが、簡単にまとめると、財政は公共事業費や社会保障関係費などの増加によってそれなりに拡大を続けました。しかし、高度成長に支えられた自然増収によって財源は十分に賄われ、一般会計の均衡財政原則は堅持されました。他方の税制は、高度成長期の租税政策として、①一貫した減税政策②強力な租税誘因政策(優遇措置)が行われました。急速な成長に伴う国民の税負担の増大を背景に、政府は経済成長で年々増大するこの財源を、西欧諸国のように政府支出の拡大には用いず、減税に充当する政策を採用したのです。
60年代前半に入ると、景気の後退局面を迎えることで自然増収にもかげりが見られ、その後は高度成長を支えるための財源として、いよいよ公債発行の必要性が議論されるようになりました。
2-2財政運営の転換期
図2-1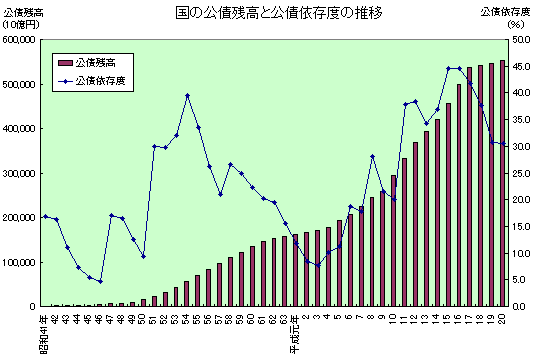
注:普通国債の残高。18年度までは実績額。19、20年度は見込み額。
(出所:第59回『日本統計年鑑 平成22年』
http://www.stat.go.jp/naruhodo/c1data/13_03_stt.htm)
65年は日本の財政にとって極めて重要な年でした。1947年の財政法制定以来、長期にわたって維持されてきた「公債不発行主義」からの転換、つまり初めて特例公債(赤字公債)が発行されたのです。図2-1が昭和41年(1966年)からのデータになっているのもそのためです。ここでの「公債不発行主義」は、一般会計における長期普通内国債に限定した狭義のものでしたが、それでも20年近くもそれを維持したことは注目に値します。
公債発行の背景としては、景気過熱による国際収支の悪化から、金融の引き締めに転じたので不況期に入っており、法人税収が伸び悩んでいたことがあります。加えて、所得税を中心に減税も実施されていたために税収が明らかに不足していたのです。こうして65年度予算は当初は均衡予算でしたが、公債発行を盛り込んだ補正予算を組むことで歳入補填をし、更には財政による景気の下支えという政策手段としての役割も担うようになりました。翌年には当初予算から建設国債を発行し、有効需要の拡大を図るとされました。要するに、65年以降の日本の財政は、「国債を抱いた財政」という、新たな局面に入ったのです。
とはいえ、政府は公債政策によるインフレや安易な公債依存に対する問題意識もあったため、建設公債の原則や市中消化の原則を堅持し、69年には「減債制度」も確立しました。更に翌年には「財政硬直化」打開のキャンペーンが打ち出され、66年後半から70年までの「いざなぎ」景気も相まって、公債依存度は急速に低下していきました。
2-3経済構造の転換期
70年代に入ると「いざなぎ景気」も終わりを迎え、景気後退局面に入りました。この時期は国際社会においても大きな変化が生じており、日本もその影響を大きく受けました。例えば、日本経済の最初の混乱は71年のニクソンショックです。これによって戦後一貫して採用してきた1ドル=360円の固定為替レートは308円に切り上げられた。この円切り上げは日本の輸出産業に少なからず影響を与え、実質成長率を低下させました。また、73年には第1次石油ショックが勃発し、スタグフレーションの局面を迎えました。更に74年には戦後初の実質成長率ゼロを記録しました。その後の回復力も弱く、以前のような力強い経済成長に戻ることはありませんでした。ここで高度成長の終焉を迎え、いわゆる「安定成長」へと移行していったのです。
参考文献
・石弘光『現代税制改革史』東洋経済新報社、2008年、167-176、327-330頁
・後藤道夫『反「構造改革」』青木書店、2002年、130頁
・納富一郎、岩元和秋、中村良広、古川卓萬『戦後財政史』税務経理協会、1988年、109-111、204-209頁
・山口公生『図説 日本の財政』東洋経済新報社、2011年、354-356頁



